愛犬もやっているかも!?犬が夜中に突然吠える”本当の理由”
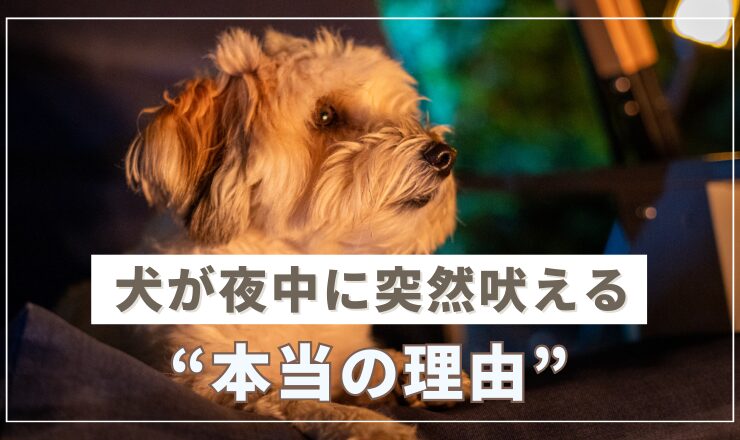
愛犬が夜中に突然吠え始めて、びっくりして起きた経験はありませんか?隣近所への迷惑も気になるし、何より「なぜ急に?」と心配になりますよね。実は、犬の夜間の吠えにはちゃんとした理由があるんです。今回は、その本当の原因と対策について詳しく解説していきますね。
犬が夜中に吠える主な理由とは?

1. 聴覚の敏感さによるもの
犬の聴覚は人間の約4倍も敏感だと言われています。私たちには聞こえない小さな音でも、犬にとっては気になる音として感じ取ってしまうんです。
よくある音の例
- 遠くを走る車の音
- 近所の猫の鳴き声
- エアコンや冷蔵庫の作動音
- 隣の家から聞こえる生活音
- 風で揺れる木の枝の音
特に夜は周囲が静かになるため、昼間は気にならなかった音でも、犬には大きく聞こえてしまうことがあります。
2. 警戒心からくる防衛本能
犬は本来、群れを守る習性を持つ動物です。家族を「自分の群れ」と認識している犬は、夜間に何か異変を感じると、家族を守ろうとして吠えることがあります。
警戒の対象となるもの
- 玄関前を通る人の足音
- 野良猫や他の動物の存在
- 見慣れない車両の音
- 不審な影や動くもの
この場合の吠えは「侵入者警報」の役割を果たしているんですね。
3. 分離不安による寂しさ
犬は社会性の高い動物なので、一人でいることに強いストレスを感じる子もいます。特に飼い主さんとの距離が離れている夜間は、不安になって吠えることがあります。
分離不安のサイン
- 飼い主が寝室に入ると吠える
- 一人でいる時間が長くなると吠える
- 留守番中も吠え続ける
- 破壊行動を伴う場合もある
4. 体調不良や痛みのサイン
意外と見落とされがちなのが、体調不良による吠えです。犬は痛みや不快感を言葉で伝えることができないため、吠えることで訴えかけている場合があります。
注意すべき症状
- 普段と違う声で吠える
- 吠える以外にも元気がない
- 食欲不振や下痢などの症状
- 特定の部位を気にする仕草
- 歩き方がおかしい
5. 認知症の初期症状
高齢犬の場合、認知症の影響で夜間に吠えることがあります。昼夜の区別がつかなくなったり、混乱状態になったりすることで起こる現象です。
認知症の兆候
- 夜中に徘徊する
- 同じ場所をぐるぐる回る
- 飼い主を認識できない時がある
- トイレの場所を忘れる
- 睡眠パターンの変化
夜中の吠えを改善する効果的な対策

基本的な環境改善
静かな環境作り
- 寝室を犬のいる部屋から離す
- 遮音カーテンや防音材の使用
- 外の音が聞こえにくい場所にハウスを設置
安心できる空間の提供
- 愛犬専用のベッドやブランケット
- 飼い主の匂いがついたタオル
- 適度な明かり(完全に真っ暗にしない)
日中の過ごし方を見直す
十分な運動量の確保 適度な疲労感は良質な睡眠につながります。犬の年齢や体力に合わせて、散歩や遊びの時間を調整しましょう。
規則正しい生活リズム
- 毎日同じ時間に食事
- 決まった時間の散歩
- 就寝時間の固定
トレーニングによる改善
「静かに」しつけの練習 吠えている時に「静かに」と声をかけ、吠えやんだらおやつをあげる練習を繰り返します。根気よく続けることが大切です。
無視する方法 構ってほしくて吠えている場合は、あえて反応しないことも効果的です。吠えても何も起こらないことを学習させます。
専門家に相談すべきケース

以下のような場合は、獣医師やドッグトレーナーに相談することをおすすめします。
- 突然吠えるようになった
- 吠え方に変化がある
- 他の症状も併発している
- 改善の兆しが見られない
- 近所からクレームが来ている
特に体調面での変化が疑われる場合は、早めに動物病院で診てもらいましょう。
まとめ:愛犬の気持ちを理解することが大切
犬の夜間の吠えには必ず理由があります。まずはその原因をしっかりと見極めることが、効果的な対策の第一歩です。単に「うるさいから」と叱るのではなく、愛犬が何を伝えようとしているのかを理解する姿勢が重要ですね。
適切な対策を継続的に行えば、多くの場合改善が期待できます。ただし、急な変化や改善が見られない場合は、専門家のアドバイスを求めることも大切です。愛犬との快適な共同生活のために、根気よく取り組んでいきましょう。

